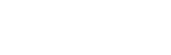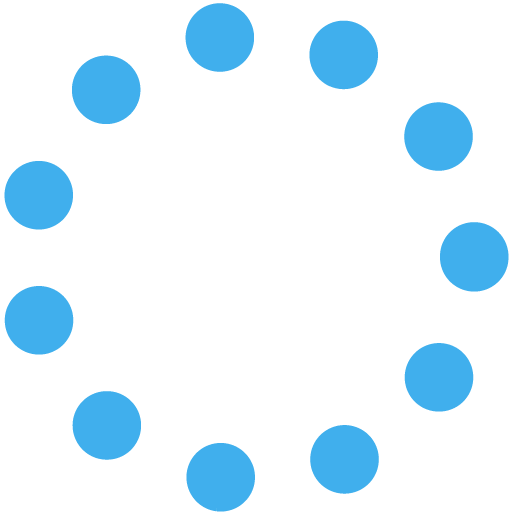こんにちは。
大阪府池田市で発達が気になるお子さん、学習につまずきのあるお子さんの教室をしています、作業療法士の中西亜弥です。
リィーノこどもセラピーでは、将来のお仕事から逆算して今子どもたちが必要な力を遊びや学習を通してサポートをさせていただいています。また、保護者、保育士、教職員の先生方に向けた研修や講演活動を行っており、その学びを深める場として“リィーノ発達ゼミ”も運営しています。
今回は、兵庫県川西市の就学前施設(保育所・幼稚園)に勤務されている先生方を対象に、「生きる力を育む保育〜器用さを育む手の発達について〜」をテーマとした研修を担当させていただきました!
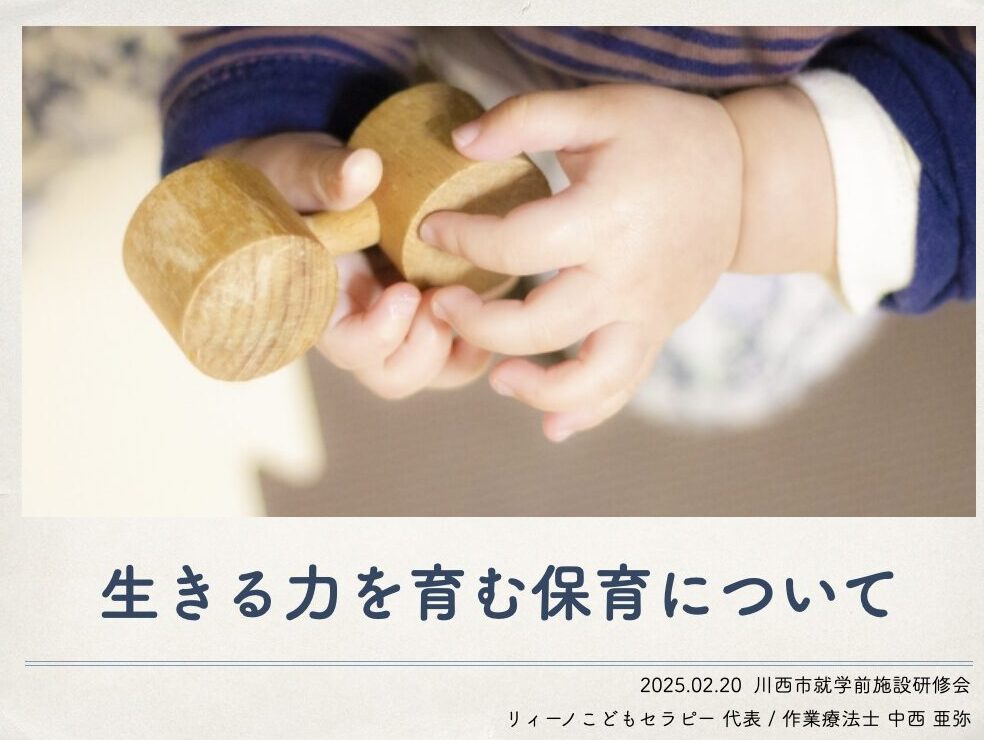
「スプーンが使えない」の背景には、理由があります。
現場の保育士さん、幼稚園の先生方から
「スプーンの三指持ちがうまくできない子が増えている」
「スプーンからお箸になかなか移行できない」
「食事中によくこぼす」
といったご相談をよくいただきます。
スプーンやフォーク、お箸などの道具操作には、
「体幹や肩周りの安定、腕をひねる動き、手指をばらばらに動かす力、力加減の調整」など
さまざまな運動発達の要素が関係しています。
また、手の発達には段階があります。
うまくスプーンを使えない子どもたちは「できない」のではなく、スプーン操作に必要な“前段階の発達”が十分に獲得しきれていないのかもしれません。
保育士さんの声から実現した研修
今回の研修は、約90名の先生方にご参加いただき(多さにびっくり!笑、対面とオンラインのハイブリット形式で実施しました。
実はこの研修、2024年度の夏に実施した川西市教職員研修に参加してくださった保育士さんからのご要望により実現したものです。
「先生のお話を、今度は保育士向けにお願いしたいです!」
とありがたい声をいただき、テーマを「就学前の生活動作」にフォーカスし、「手の発達段階」と「支援につながる遊び」を実践的にお届けしました。
スプーンを使った“不器用さを体験する”ワーク
今回は、手の発達についてのお話と、スプーンの操作の体験ワークを組み合わせた構成で実施しました。
体験ワークでは、
・手のひらを下にしたままスプーンを持ってみる
・体幹を全くひねらない状態でスプーンを使ってみる
といったルールを設けた中でスプーンを使ってみることで、子どもが感じている“うまくできない理由”を体感しながら考えていただきました。
また、手の発達のお話では、0~1歳までの運動発達と手の発達の関係性についても解説し、乳児期の運動遊びや感覚遊びが、スプーン操作などの生活動作の土台になることもお伝えしました。
 不器用さを体感するワーク
不器用さを体感するワーク
「手のひらを下に向けたままスプーンを持ってみよう!」
参加者の声(一部抜粋)
実際に参加された先生方からも、子どもを見る視点が変わったという声を多くいただきました。
ここでは、その一部をご紹介します^^
🗣️実際に食具を使い、子どもがどんなふうに感じたり、困ったりするかに気づきました!
🗣️遊びだけでなく、生活面でも手の発達につながることがたくさんあると分かった。
🗣️“不器用”という言葉の捉え方、それを指す意味がいつも気になっていたので詳しく聞くことが出来て学びになった。
🗣️実際にスプーンを持って、様々な条件で試してみることで、疲れる、食べこぼしが多い、姿勢が崩れるなど、気になる子どもへの見方が変わりました。
🗣️体幹をひねらない、手のひらを下にしたままなど、いろんなスプーンの持ち方を実際にしてみることで声かけの内容もかわること、この事は“目からうろこ”が落ちる感覚だった。
🗣️スプーンを持つときに薬指と小指を伸ばして三指握りしている子どもへの援助の仕方も、具体的に教えてくださり、大変勉強になりました。
研修・講演のご依頼について
リィーノこどもセラピーでは、
保育園・幼稚園・学校・療育機関のスタッフ様向けに、
子どもの発達や支援に関する実践的な研究・講演のご依頼を承っております。
▶︎研修のご相談・ご依頼は こちら から
もっと気軽に発達支援のヒントを受け取りたい方へ
リィーノこどもセラピーのインスタグラムでは、
・子どもたちの“うまくできない”についてエビデンスに基づいた理由
・おうちで楽しく簡単に必要な力を育む遊びや活動
などをスキマ時間で読める形で配信しています!
よければフォローして、日々の関わりのヒントに役立ててくださいね✨
▶︎リィーノこどもセラピーのInstagramアカウントは こちら