お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります
ファイルにプリントが綴じれない!どうしたらいいの?
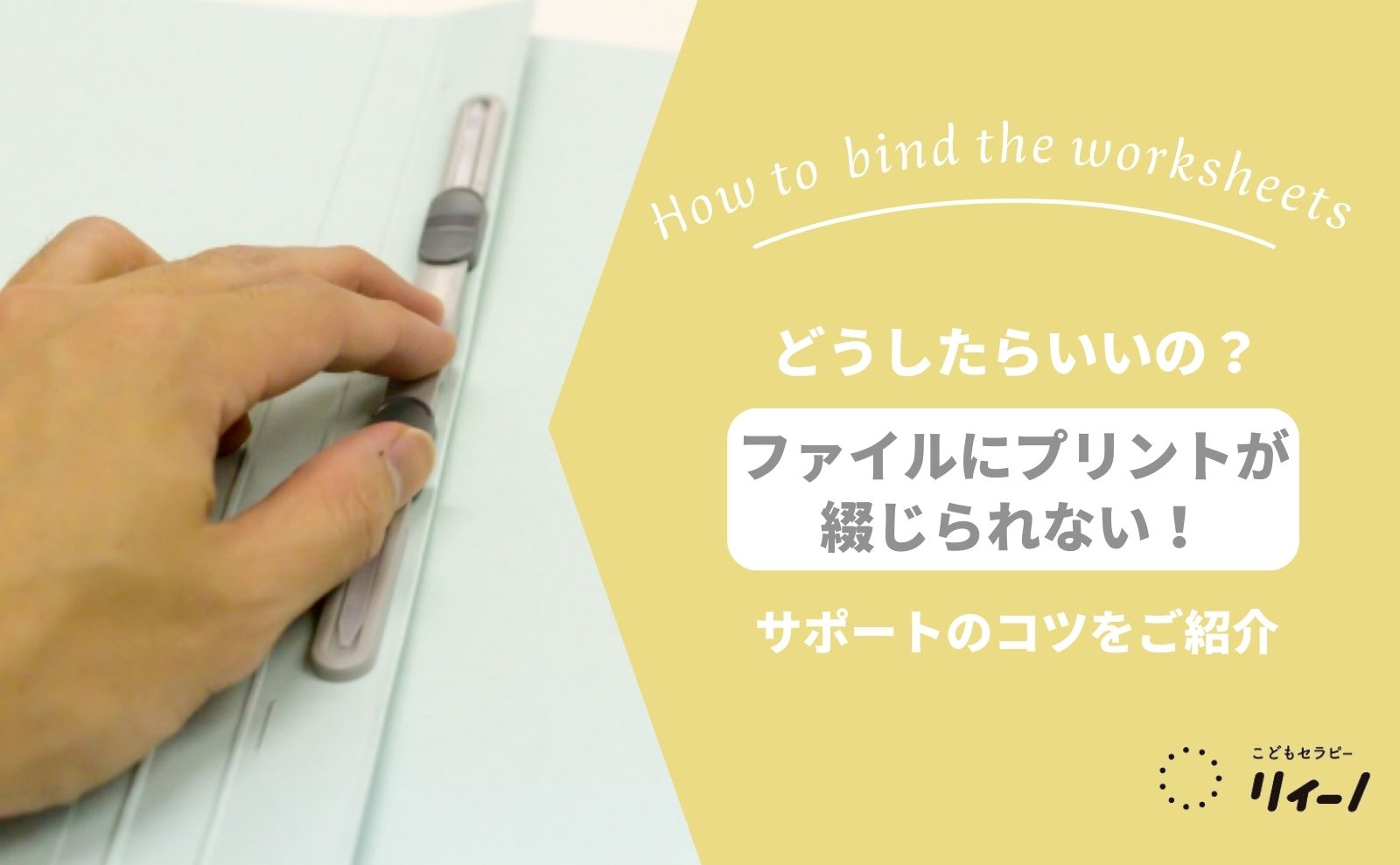
プリント整理についてこんなご相談をママからいただきました。

「ファイルにプリントを綴じなさい!」
と何度も声かけをしたり、一緒にやっているんですが、プリント整理ができず、カバンの中でぐちゃぐちゃになってしまいます。
どうしたらいいですか。
小学4年生以降になると、プリント整理のご相談を学校の先生や保護者の方からお受けすることが多くなります。
中学生になると提出物を出さなければ成績にも影響が出てしまうので、どうしたらいいのかと悩まれる方も多いと思います。
今回は、紙ファイルにプリントが綴じれない理由についてお伝えして、対策方法を一緒に考えていきたいと思います。
どうしてできないの?
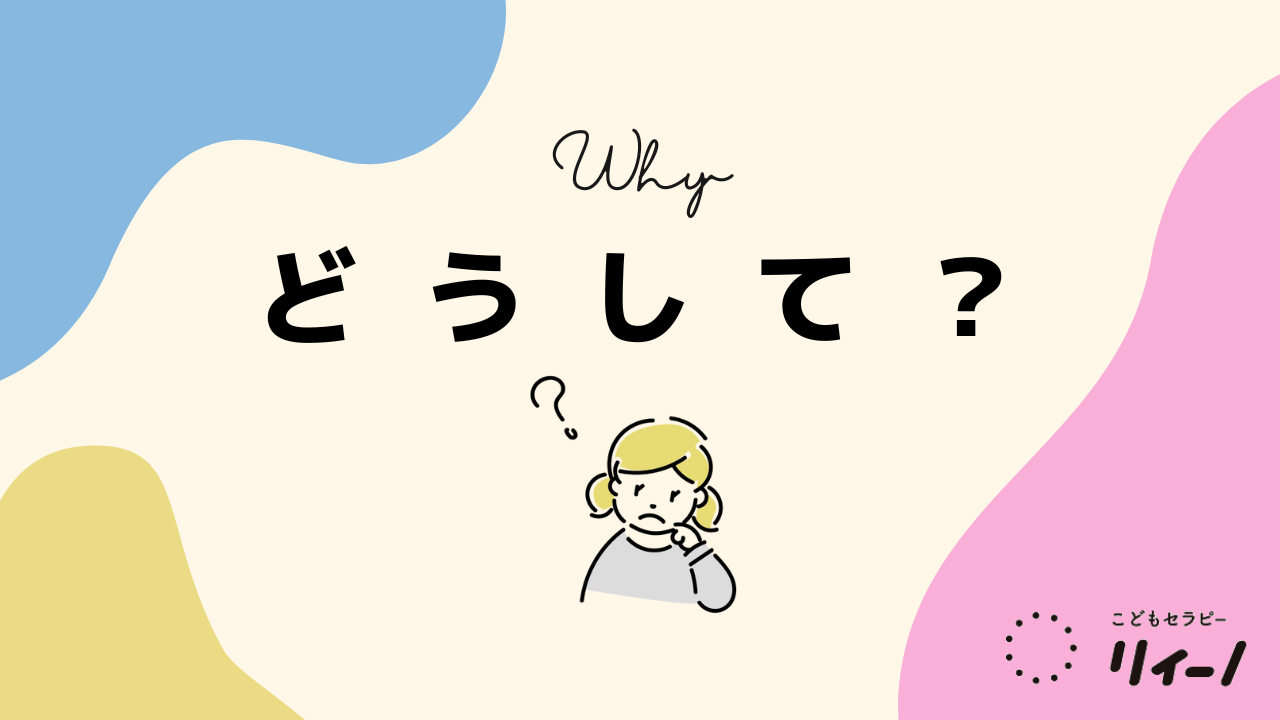
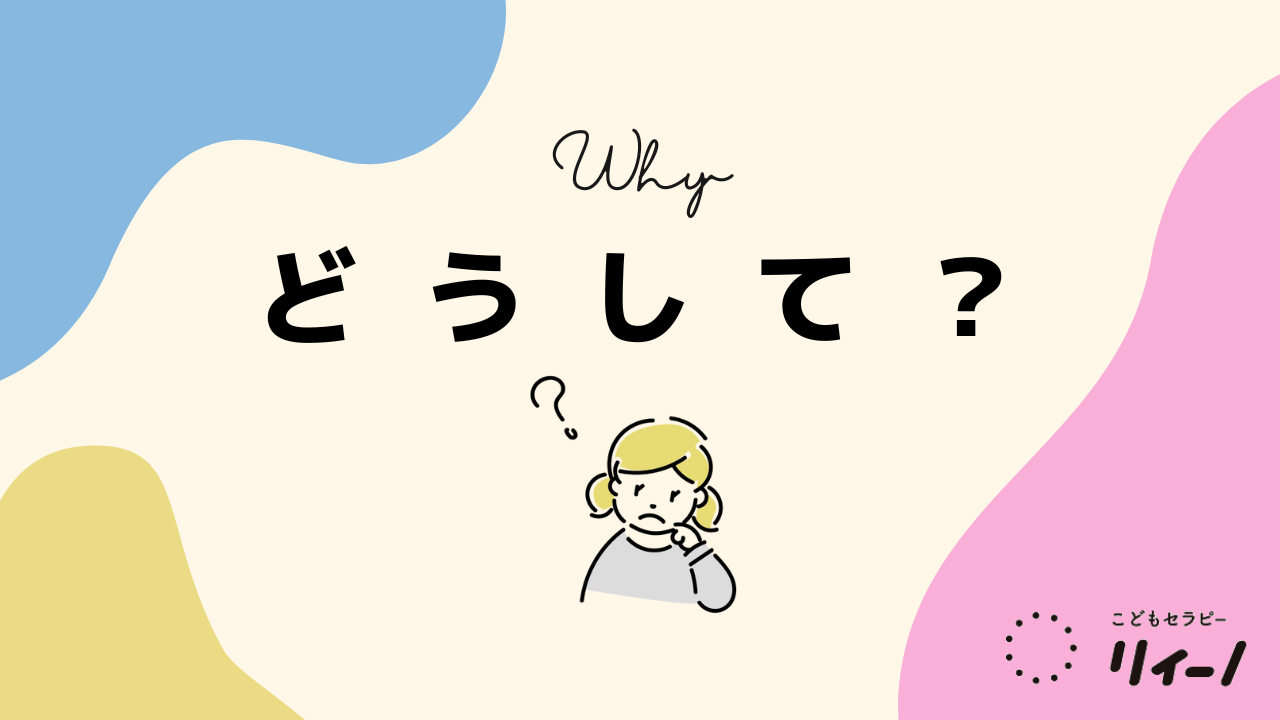
さて、なぜプリントをファイルに綴じれないのでしょう?
大人でもプリント整理が苦手な方って結構多いはず。
(私も職場ではやらねば精神でできますが、自宅ではすぐに山積みにしてしまうタイプ…笑)
プリント整理ができない理由も実はいろいろあります。
よくある理由を5つ挙げてみます。
- 言葉の意味が十分にできていないのかも
- 手順を覚えることが苦手
- 手先の細かな作業が苦手
- 集中することが苦手
- 見る力の弱さ



1つずつ解説していきますね!
言葉の意味が十分に理解できていのかも
言葉の意味といっても、幅が広すぎますよね。
まずは、紙ファイルにプリントを綴じるまでの手順を確認してみたいと思います。
紙ファイルにプリントを綴じる流れ
紙ファイルにプリントを綴じるまでの手順は、おおまかに次の5つになると思います。
- 紙ファイルの表紙を開ける
- 留め具を開ける
- プリントを留め具に通す
- 留め具を閉める
- 紙ファイルの表紙を閉じる



つまり、「ファイルに綴じて!」の一言で、これだけの手順をすぐにイメージできるかどうかということを確認してあげる必要があるんです。
私たちは、この手順を分かっている前提で「ファイルに綴じて」という言葉を使っています。
ファイルにプリントが綴じれないお子さんの中には、もしかすると、この手順のどこかが分かっていない可能性があるということです。
大人も、「コピペしといて!」「スクショしといて!」と言われて、”どうやってするんだっけ?”と初めてパソコンやタブレットを触った時に思ったことがある方も多いかもしれません。
それと同じ状況にあるかもしれないということですね。
手順を覚えることが苦手
上記の手順を覚えて、思い出す作業が必要になります。
これには、記憶力やワーキングメモリという一時的に物事を覚えたり、思い出したりするために使われる力が必要になります。
ファイルにプリントを綴じることは分かっていても、どんな手順で作業を進めたらいいのか戸惑ってしまい、うまくできないこともよくあります。
また、どの作業から始めたら良いのかという見通しを立てる力も関わってきます。
手先の細かな作業が苦手
留め具の開け閉め、留め具にパンチで開けたプリントを通すなど、ファイルにプリントを綴じるためには手先の細かな操作と目と手のチームワークが必要になります。
留め具を開けるために指先だけに力をいれることが苦手だったり、留め具にプリントを通そうと思ったら破れてしまったり。
そんなことが繰り返されると、”ファイルに綴じるのが嫌だ!”となっていてもおかしくないですよね。
集中することが苦手
ファイルにプリントを綴じるなんて数秒で終わるじゃないか…と思われるかもしれませんが、集中することが苦手な子どもたちにとっては数秒でも苦痛な時間。
特に、学校では休み時間になる直前にプリントを片付ける作業も多く、周りもザワザワし始めるため集中力が途切れやすくなります。
お友達が休み時間にでかけていきそうなのを見たら、僕も!私も!と気持ちが焦り、プリントを綴じるために手元を見て集中することが難しくなることが想像しやすいかと思います。
おうちは、ホッとできる安心・安全地帯。
日中頑張ってきた子どもたちは、疲れ果てています。
集中力の電池はほとんどなくなっているでしょう。
その状況で苦手な活動に取り組むのは、なかなか難しいことが多いと思います。
見る力の弱さ
いろんな教科でもらったプリント、保護者宛の配布物…。
たくさんの中からどのプリントを取り出し、どのファイルに綴じるといいのかといったたくさんの情報の中から必要なものだけを取り出す(見る力)も関わってきます。
手先の器用さにも関わりますが、手元を見続けたり(注視する)、留め具にきちんとプリントが通るかを確認したり(キョロキョロと目をスムーズに動かす力)。
さまざまな見る力を総動員する必要があるのです。



プリントを1枚ファイルに綴じるだけでも、いろんな育ちが必要になりますね!
どうしたらいいの?
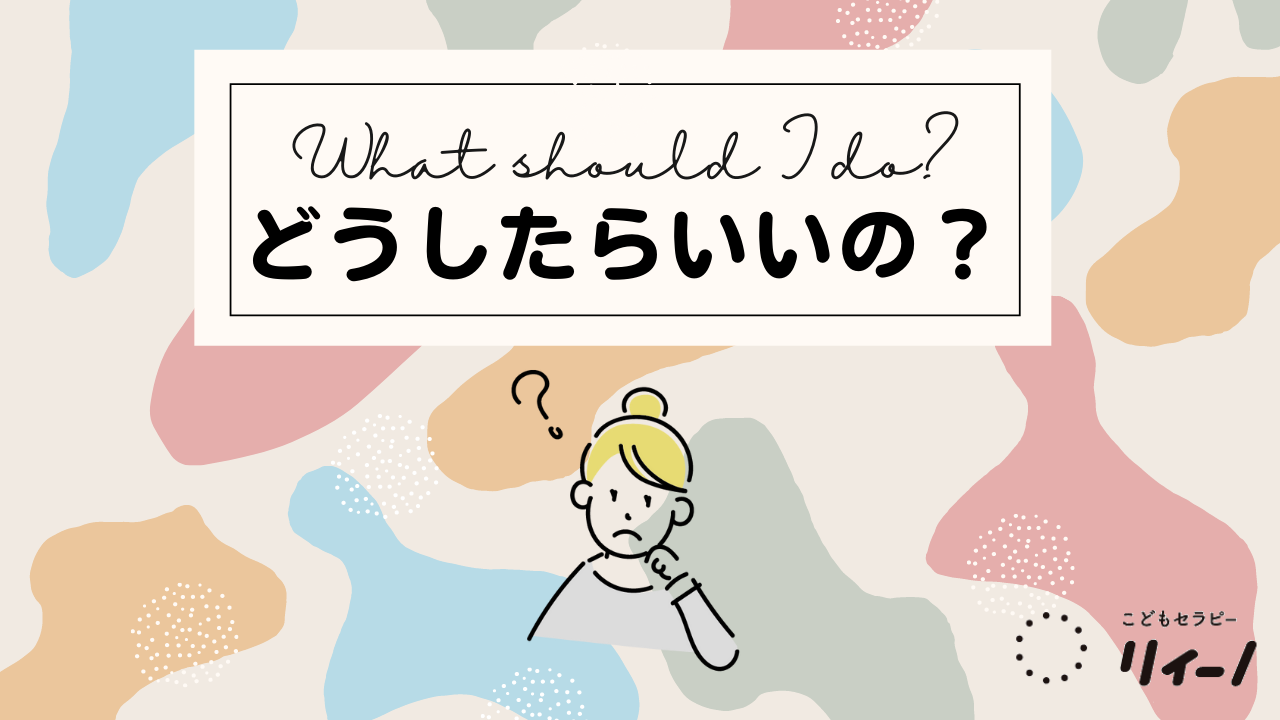
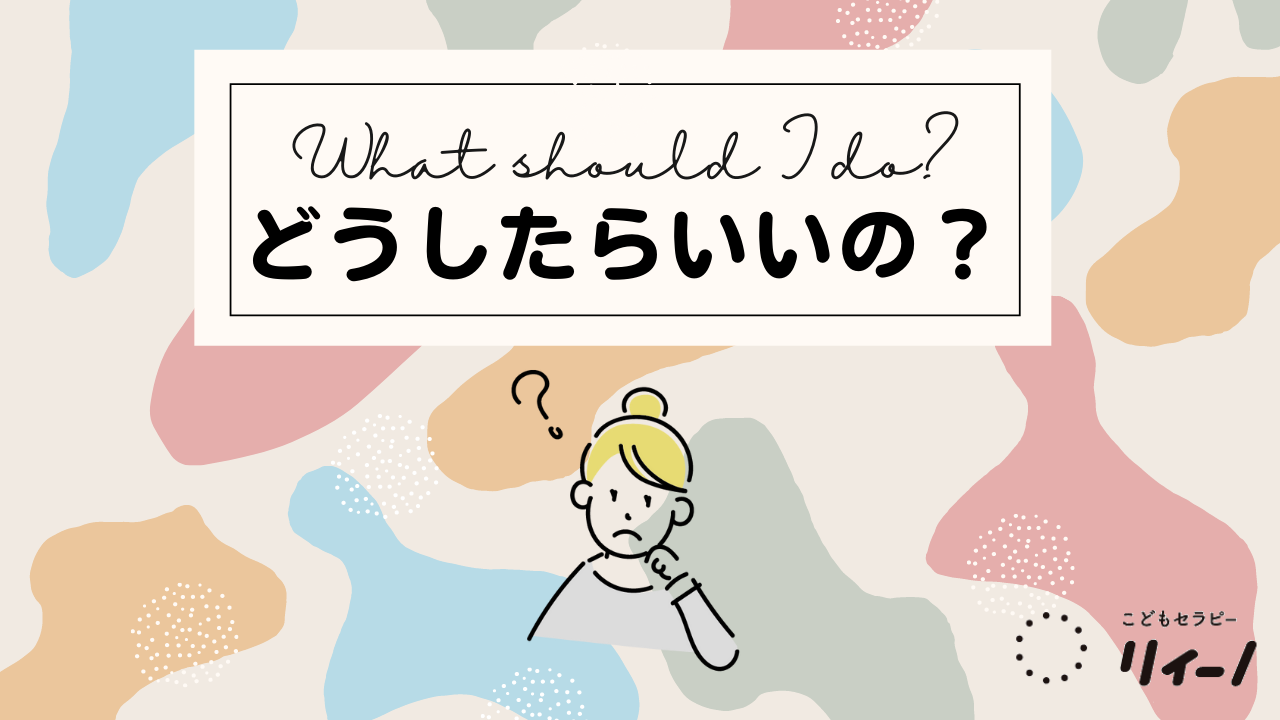
それでは、アプローチを4つ挙げてみたいと思います。
お子さんがどの方法が合うのかは、原因によって異なります。
また、紹介したアプローチを少しアレンジすることでうまくいくこともあるので、参考にしてみてください。
- 言葉の意味と手順を確認しよう!
- 手順を確認できるサポートを!
- まずは、手順の最後だけ大人と一緒に取り組む
- 使いやすいファイルを探す
言葉の意味と手順を確認しよう!
「ファイルにプリントを綴じて」という言葉には、上記のプリントをファイルに綴じるまでの流れを意味していることを伝える必要があります。
まずは、流れを理解できているかどうかを確かめてみましょう!
手順を確認できるサポートを
見て覚えやすいタイプのお子さんには、手順表を見えるところに置いておきましょう。
文字を読むことができるお子さんの場合は、上記の手順をそのまま使ってもいいと思います。文字を読むことが苦手なお子さんの場合は、工程を写真に撮ったり、イラストにしたりして見せてあげると分かりやすくなります^^
また、聞いたことを覚えやすいタイプや一つずつ伝えた方が分かりやすいタイプのお子さんには、順番に声かけをしてあげてください。慣れてきたら声かけの量を減らしていくといいと思います。
まずは、手順の最後だけ大人と一緒に取り組む
先ほどのプリントをファイルに綴じるまでの手順をもう一度確認したいと思います。
- 紙ファイルの表紙を開ける
- 留め具を開ける
- プリントを留め具に通す
- 留め具を閉める
- 紙ファイルの表紙を閉じる
この5つの手順でしたね。
最初から始めると、留め具にプリントを通すところでイライラしてしまう可能性が大です!
なので、まずは4番、5番(ピンク色のマーカー部分)の最後だけを一緒に取り組んでみましょう^^
全部させたい親心はよく分かりますが、まずは「できた!」という達成感を味わってもらうことが自立への近道です。
4番、5番ができるようになったら、少しずつ1人で取り組んでもらう工程数を増やしていきましょう!
なにごとも少しずつ、少しずつです^^
使いやすいファイルを探す
100円ショップや文房具屋さんには、たくさんの種類のファイルが売られていますね。
学校では今回ご紹介した紙ファイルを使うことが多いと思いますが、使いやすさは人それぞれです。
どのファイルがお子さんに合うかどうか困ったら、作業療法士と一緒に考えましょう^^
いきなりファイルに綴じるところからスタートせずに、まずはバサッとひとまとめにクリアファイルに入れておいで!から始めてもOKだと思います。
きっと学校の先生も伝え方次第で協力してくださると思います^^
学校とおうちとうまく連携しながらサポートしていけるといいですね。
まとめ


紙ファイルにプリントを綴じるって簡単なようですが、実はさまざまな力を総動員してできているということを知っていただけたでしょうか。
では、今日のお話のおさらいです。
- 「ファイルに綴じて」は、プリントを綴じる手順を理解している前提で使っいる言葉。
- まずは、ファイルに綴じる手順を知っているかどうか確認する。
- ファイルに綴じるには、いろんな育ちの力が必要。
・言葉の意味を理解していること
・手順を知っていて、その方法を思い出すことができること
・手先の器用さと見る力の合わせ技が必要なこと
・数秒でも集中力が大きく関わっていること - 手順を思い出せるようなサポートを。
- まずは最後の工程だけ取り組むこと。
- お子さんに合ったファイルの選択を。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!