お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります
鉛筆がうまく持てない!正しく鉛筆を持つにはどうすればいいの?
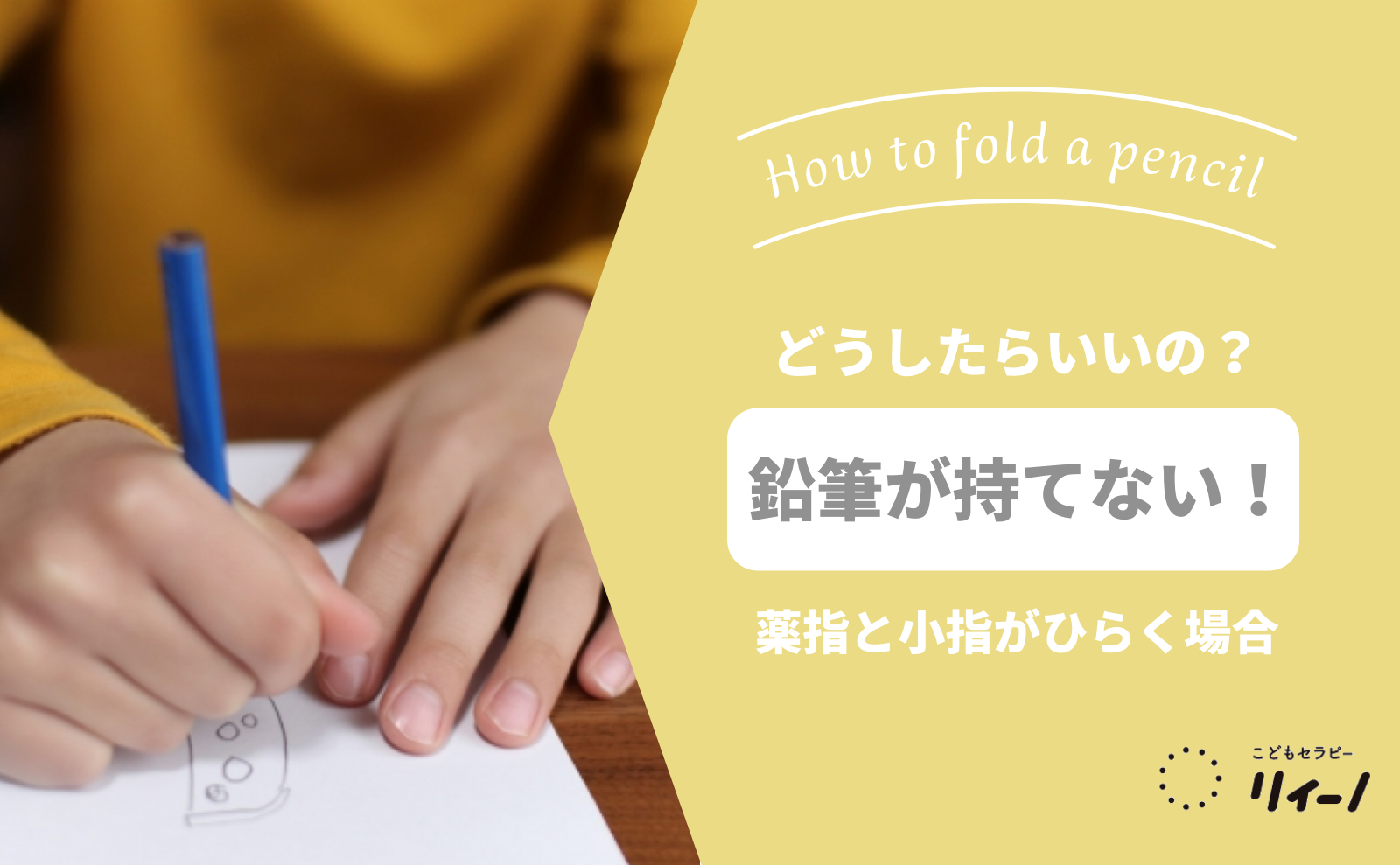

市販の補助グッズを試してみたけど、正しく鉛筆が持てないです。
どうしたらいいですか?



正しい持ち方で持って欲しいけど、持ち方を指摘すると嫌がるので、どう教えたらいいのか困っています。
鉛筆の相談件数ダントツ1位!
癖付くまでになんとかしたいと思っている方は多いと思います。
鉛筆が持てない理由は、お子さん一人一人異なることがほとんど。
指先の練習だけをしても上手くいかないことがほとんどなんです。
今回は、サポートの一例と鉛筆を正しく持つことに繋がる遊びをご紹介したいと思います。
- 鉛筆をしっかりと持つことができない。
- 鉛筆を持つと首から手にかけて、とても力が入ってしまう。
- 市販の補助グッズを使ってみても、なかなか正しい持ち方にならない。
- 変な持ち方の癖が付くまでに、正しい持ち方を覚えて欲しい。
鉛筆の持ち方を確認しよう!
今の鉛筆の持ち方を確認してみよう



お子さんの鉛筆の持ち方を確認してみてください。
このとき、指先だけを見るのではなく、「首や肩などに力が入っていないか」「どんな姿勢で書いているか」チェックしてみてください。
下記のような様子は見られませんでしたか?
- 薬指と小指が開いている。
- 薬指と小指にすごく力が入っている。
- 首や肩、腕全体に力が入っている。
- 鉛筆の先が自分の方に向いている。
- 椅子に座っているとき、姿勢が崩れやすい(左右に傾く、ずれ落ちているなど)。
このような持ち方をしている場合は、ものすごく頑張って鉛筆を持っている状況です。
そのため、とっても疲れやすかったり、適度な筆圧で整った文字が書けなかったり、ということが起こってしまいます。



持ち方が気になるとは思いますが、この状況にある子どもたちは、“毎日とっても頑張って文字を書いている”ことを知っていただけると嬉しいです。
正しい鉛筆の持ち方とは?
正しく鉛筆を持っているとき、姿勢や指先はどのようになっているのでしょうか。


- 首や肩、腕全体にはあまり力が入らない。
- 指先は、薬指と小指は軽く丸めた状態になる(上記の写真の赤丸)。
- 鉛筆を動かすとき、主に親指・人差し指・中指の3本を使う。
- 鉛筆の先が前方に向いている。
- 少し前かがみの姿勢をキープしながら、椅子に座っていられる。
鉛筆を正しく持つには、どうしたらいいの?
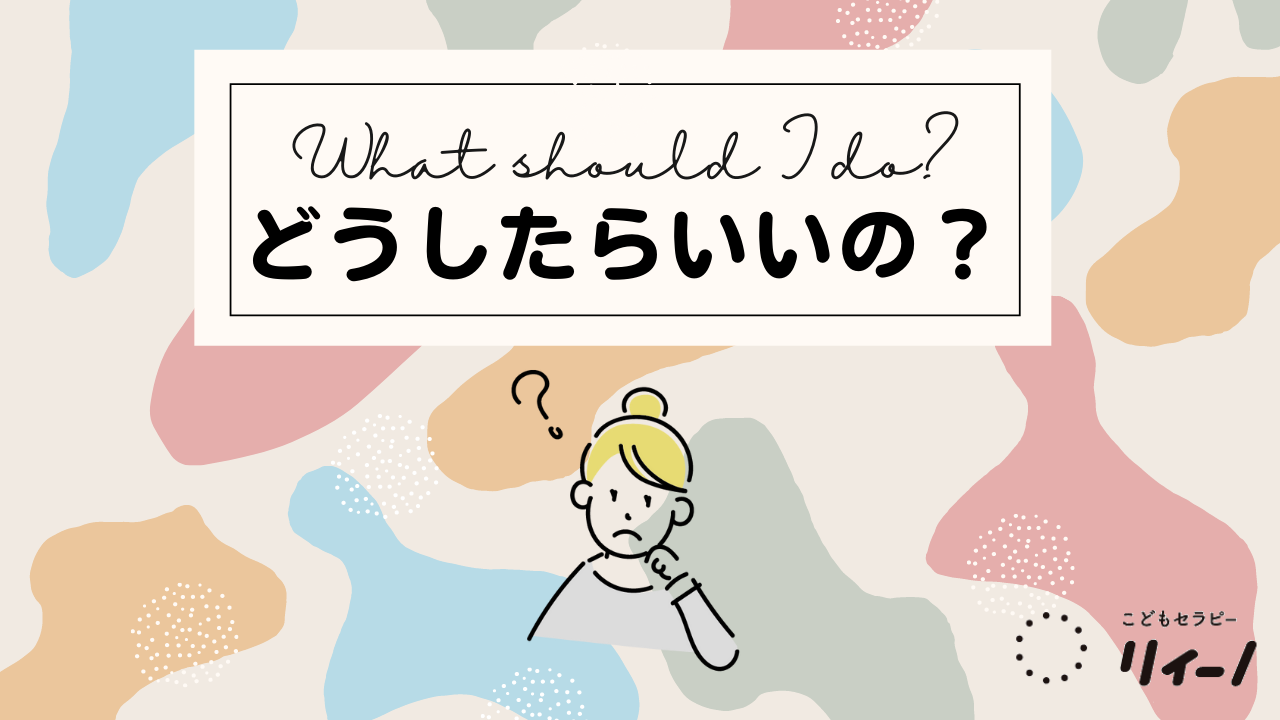
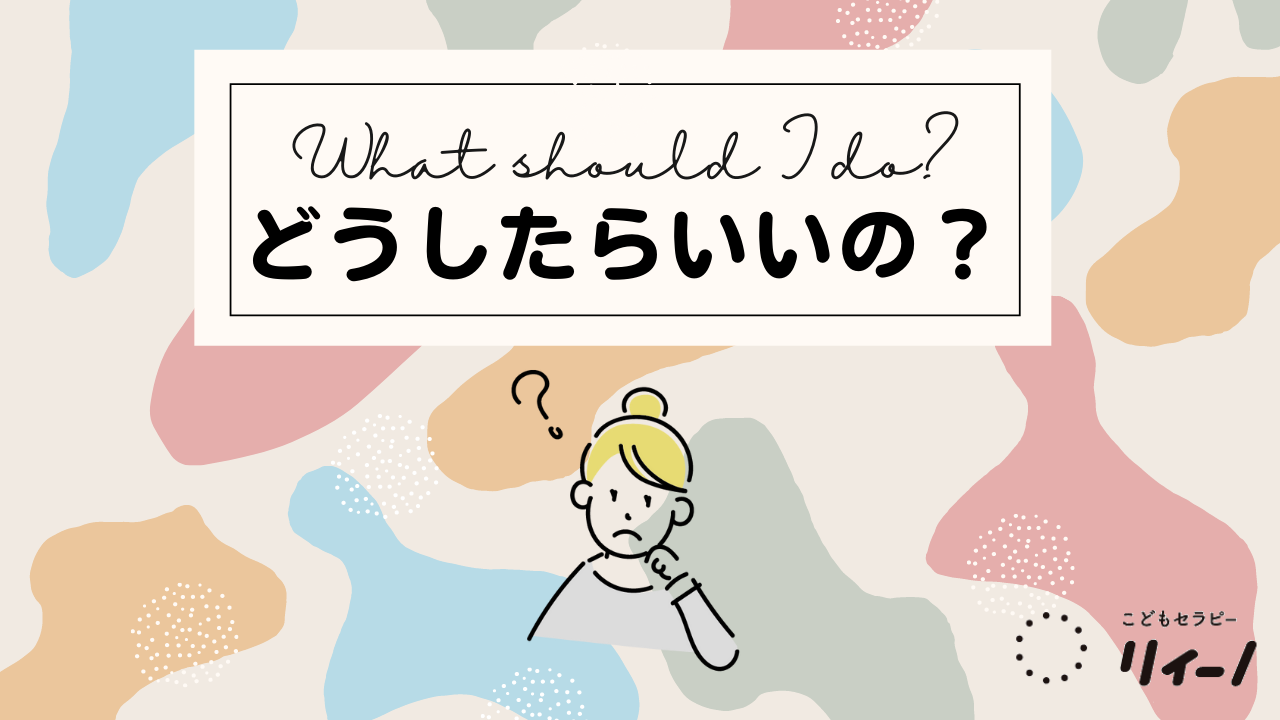
薬指と小指でビー玉を握ってみよう
薬指と小指でビー玉やティッシュを丸めたものを握ってもらってください。
握るものがあることで、薬指と小指に適度な力が入り安定しやすくなります。
そして、薬指と小指に力が入ることがわかると、首や肩の力が抜けて、親指・人差し指・中指が動きやすくなります。
※下記のInstagramの5枚目に動画があるので、ご参照ください。
ビー玉やティッシュを毎回持ち直すのは面倒だったり、ビー玉が転がっていくと集中力も途切れてしまいますよね。
リィーノの子どもたちには、ループエンドにパンツのゴムを通して輪っかを作り、薬指と小指に引っ掛けて持ってもらっています。
まずは、このやり方が合うかどうか試してみてくださいね。
ループエンドとは、巾着袋の先についているビーズのことです。(これ↓)
持ってもらうときの声かけのヒント
はじめてのものに興味を示して持ってくれる子、今までと違うことを導入されることにドキドキしてしまう子。
いろんなタイプのお子さんがいらっしゃいますよね。
私がビー玉やループエンドを最初に試してもらうときに、お願いする声かけのヒントをご紹介します。
上手に書けるおまもり



上手に書けるようになるお守りだよー^^
お姉さん指と赤ちゃん指でお守りをしっかりと握っててね!
“お守り”というワードが、子どもたちにはイメージしやすいようです。
他にも、“魔法をかけるね”という表現の方がやる気に満ち溢れるお子さんもいらっしゃいます。
たまご持っててね



お姉さん(指)と赤ちゃん(指)に卵を持っててもらってくれる?
握り込んでも、落としても割れちゃうから、気をつけてね。
どの程度力を入れたらいいかが分かりにくいお子さんには、力加減がイメージしやすい伝え方をしています。
お姉ちゃんと赤ちゃんだけ寝ててね



お兄さん(指)は、起きててねー!
お姉さん(指)と赤ちゃん(指)は寝ててね(お休みしててね)
中指も一緒に握り込もうとしてしまうお子さんには、中指は鉛筆を動かすことに使うことを意識してもらうために伝えています。
最初の○○だけ持っててね



最初の1分だけ持っててね!
最初の1行だけ持って書いてみてね!
持つことに対して抵抗のあるお子さんには、いつまで持てばいいのかを明確に伝えるのが効果的です。
声かけは、ヒットする日もあれば、ヒットしない日もあるものです。
お子さんが興味のあるものに例えて伝えてあげると、うまくいくかもしれません。
声かけをいろいろと変えてみてもうまくいかない場合は、持つことがいやなのかもしれません。
無理強いはせず、他の方法を考えみましょう。
鉛筆を正しく持つ力に繋がるあそび


引っ張るあそび
そり遊びや綱引きのような手のひら全体で握って引っ張る遊びは、薬指と小指に力がしっかりと入ります。
薬指と小指は、ものの操作をするときに安定性を高める役割があります。
薬指と小指にギュッと力を入れる活動をすることで、5本の指をバラバラに使う土台を育むことに繋がっていきます。


また最近は、バリアフリーの影響で引き戸がないおうちが多くなってきています。
子どもたちは、生活の中で“引っ張る”“押す”という運動の経験がなかなかできなくなってきています。
これらの運動を少し意識して生活や遊びの中で取り入れてもらうことで、子どもたちの発達を促す手助けをすることができます。
タオルを使って引っ張り合いっこをすれば、おうちでも簡単にできるので挑戦してみてください^^
重たいものを運ぼう
ペットボトル500〜1000mlなど重さのあるものを、袋に入れて両手でしっかりと握って運んでもらってください♪
重たいものを運ぶとき、自然と薬指と小指を握り込んで支える力を育むことができます。
お買い物に行ったときは、ママのお手伝いも兼ねてたくさん持ってもらいましょう^^
トイレットペーパーを買ったときは、絶好のチャンスかも♪
どうして正しく鉛筆を持つことができないの?


- 5本の指をバラバラに動かすことが苦手
- 腕・手首を滑らかにうごかすことが苦手
- 姿勢を保つことにパワーを使っている
1つずつ解説していきますね。
5本の指をバラバラに動かすことが苦手
5本の指にはそれぞれ役割があります。
- 親指・人差し指・中指は「操作する」こと。
- 薬指と小指は、「支える」こと。
人間の手は、小指側から発達していきます。
この薬指と小指の支える力が育ちきっていないと、物の操作がとてもやりづらくなってしまいます。
腕・手首を滑らかにうごかすことが苦手
鉛筆を持つためには、手のひらを返す動き(腕の動きになります)、手首をあげる動きが必要になります。
鉛筆の先が自分の方に向いていたり、鉛筆を筆のように上の方を持っていたりする場合は、腕や手首を滑らかに動かすことが苦手なのかもしれません。
姿勢を保つことにパワーを使っている
鉛筆を持って文字を書くためには、体幹の安定性が欠かせません。
椅子に座って姿勢を保つだけで、パワーを使い果たしている可能性があります。
首や肩にものすごく力が入っていたり、椅子から落ちそうになっていたりする場合は、楽に座れる環境を整えることで鉛筆の操作がしやすくなる子もいますよ。
鉛筆は持てているのに、文字がマス目から大きくはみ出たり、字が書けない場合は、他に理由があることもあります。
詳しくは字が書けない、マス目からはみ出る。その原因と楽しく育むコツを読んでみてください。
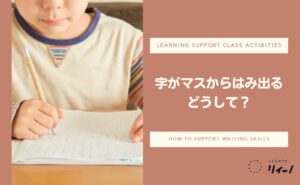
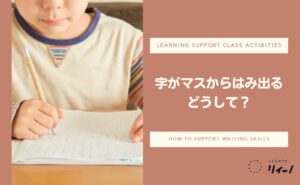
まとめ


いかがでしたでしょうか。
鉛筆の持ち方は、指先だけでなく全身の身体の使い方が影響しています。
ビー玉を握るのを嫌がる場合は無理強いはしないこと。
必ず違うアプローチの仕方がありますので、うまくいかない場合はいつでもご相談ください。
今回の内容のまとめです。
- まずは、お子さんの鉛筆の持ち方を観察して、薬指と小指の状態を確認してみよう。
- 薬指と小指の安定性を高めるために、ビー玉をおまもり代わりに握ってもらおう。
- 引っ張ったり、重たいものを運んだりする遊びやお手伝いをして、薬指と小指の力を育もう。
- 姿勢が崩れやすい場合は、楽に座れる環境を検討してみよう。