お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります
前庭覚ってなあに?【自分の身体を知るための感覚】


うちの子、ブランコでなかなか遊べないんですがどうしてですか?



学校の板書に苦労しています。漢字の宿題もとても時間がかかってしまいます。なぜでしょう?
保護者や巡回相談先の保育士さんや学校の先生からお受けする上記のようなご質問。
これらのつまずきの背景には「
今回は、7つの感覚の1つである「



“前庭覚”は、一般的に“三半規管”と呼ばれている感覚と似ています。
この働きについて知ると、子どもたちの不思議な言動の理由が見え、具体的な対応策を練ることができますよ^^
7つの感覚については、「感覚」ってなあに?運動・学習・社会性の基盤となる7つの感覚の記事で説明しています。


前庭覚がうまく働かないとどうなるかについては、「前庭覚」がうまく働かないとどうなるの?の記事をお読みください。
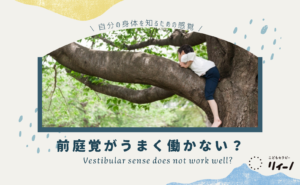
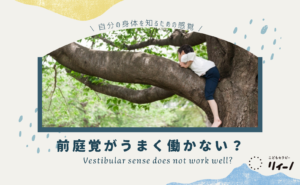
前庭覚のはたらき
前庭覚といわれるとイメージしにくいと思いますが、一般的によく言われる「三半規管」のこと※1をイメージすると捉えやすくなると思います。
※1
三半規管は、耳の奥(内耳)にある平衡感覚を司る器官のことをいいます。
なので、前庭覚=三半規管ではありません。
前庭覚には、大きく3つの働きがあります。
これらの働きによって、私たちは支障なく生活を送ることができているのです。
- 姿勢の保持や運動に関わる
- 学習の基盤となる
- 気持ちのコントロールの土台となる
それでは、1つずつ見ていきましょう!



前庭覚は、単独で働くわけではありません。
他の6つの感覚との合わせ技で、上記の7つのお仕事を常にしてくれています。
❶ 姿勢の保持や運動に関わる
前庭覚は、今自分の身体がまっすぐなのか、傾いているのかといった自分の姿勢の状態を教えてくれます。
下の写真のお子さんを例に挙げてみましょう。


ボールで遊ぶために“安定した姿勢になっているよー!(身体がまっすぐだよー、傾いているよーなど)と常に身体の状況を前庭覚のセンサーが感じ取って、脳に情報を送っているのです。
姿勢が崩れそうになったら、元の位置に戻ってきてー!と脳から指令が出されます。
また、姿勢が崩れないように、その活動をするために適した姿勢が取れるために、適した筋肉の張り具合(筋緊張)を調整したり、バランス感覚も担っています。
❷学習の基盤となる
7つのどの感覚も学習の基盤となりますが、特に学校での学習に大きく影響するものが前庭覚かもしれません。
というのも、前庭覚は眼球の運動コントロールと密接に関わっているからです。
ちょっとここでプチワークをして、みなさんに体感してもらおうと思います。



このブログをスマホやタブレットで読んでくださっている方は、それを持ったまま目の高さで、手を振ってみてください。
文字を読むことができましたか?



読めません・・・!



そうですよね。
では今度は、スマホまたはタブレットを持ったまま手は動かさず、頭を上下左右に振ってみてください。
文字は読めたでしょうか?



わあ!読めた!不思議ー!!
これは、頭の傾きに合わせて、目をピピピと動かして、文字がブレないように瞬時に調整してくれているからなんです。
頭の傾きに合わせるというのは、先ほど説明した姿勢がどうなっているかを教えてれる前庭覚の働きの1つですね。
このように、前庭覚のはたらきのおかげで、常に姿勢の状態を教えてもらいながら、目の動きと連携して私たちは文字を読んだり、街中をふらつくことなく歩いたりすることができています。
さて、学習の基盤の話に戻りましょう。


幼稚園に入園すると、色塗りをしたり、折り紙を折ったり、パズルをしたり。
小学校に入学すると、板書をしたり、左に置いたドリルを見ながら文字を書いたり、本読みをしたり。
このように、見て作業する活動がたくさん増えますよね。
これらの作業をするためには、安定した姿勢を保ちつつ、首や目を常に動かして取り組まなければいけません。
つまり、先ほどの体験ワークでしてもらったように、学習をするためには目と頭の動きの連携プレーが欠かせないのです。



学習に集中できない、整った文字が書けないなどのご相談をよくお受けします。
ふざけたり、集中しないのではなく、この前庭覚の働きや目の動かし方がうまくいかず、うまくできないというお子さんによく出会います。
なかなか解決がしないときは、いつでもご相談くださいね。
❸ 気持ちのコントロールの土台となる
電車の揺れでうとうといい気持ちになって、眠たくなってきたことってありませんか?
反対に、遊園地に行っていろんな乗り物に乗って1日遊び倒して疲れて帰ってきたのに、なかなか眠れない…といったこともありませんか?
前庭覚は、脳の目覚めの状態(覚醒状態)にも大きく関わっています。
また、うとうとといい気分になることもあれば、刺激が強すぎてハイテンションになってしまうこともあります。
他にも、前庭覚は、自律神経と関わっています。
たとえば、車酔い。車の動きにだんだんと気持ちが悪くなってきてしまうのは、自律神経と繋がっているから起こること。
子どもたちが不機嫌になった理由として、気持ち悪くなってしまったからということも考えられるかもしれません。
このように、前庭覚は気持ちのコントロールとも密接に関わっています。
おすすめの本


感覚統合Q&A 改訂第2版 ー子どもの理解と援助のために
いつもリィーノの保護者の皆さんや保育士・教師の皆さんにことあるごとに紹介している本です。
感覚についてとても分かりやすく書かれています。
また、よくある困りごとがたくさん載っていて、なぜそれが起こるのかを感覚の視点から説明がされています。
お子さんの対応を考えるヒントになると思います。
まとめ


今回は、自分の身体を知るために必要な感覚の1つである前庭覚の働きについてお伝えしました。
運動にも、学習にも、気持ちのコントロールにも大きく関わるこの感覚について知ることで、子どもたちの捉え方は大きく変わると思います。
それでは、今回のまとめです。
- 姿勢の保持や運動に関わる
- バランス感覚
- 筋肉の張り具合(筋緊張)のコントロール
- 目の動き(眼球運動)のコントロール
- 自律神経との連携
- 脳の目覚め(覚醒)のコントロール
- 気持ちのコントロール
- 他の感覚と合わさって、姿勢や運動、学習、気持ちのコントロールの基盤に関わる。