お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります
「感覚」ってなあに?運動・学習・社会性の基盤となる7つの感覚


うちの子、“感覚過敏”みたいなんですけど、どうしたらいいですか?



“感覚が鈍い”と言われたんですけど、どういうことですか?
感覚についてのご相談はたくさん伺います。
「感覚」と言われると、なんとなく意味は分かるけど、なんだか掴みきれない。
そう思われてる保護者さんや子どもと関わるお仕事をされている方に、たくさん出会ってきました。
最近は「感覚過敏」という言葉が飛び交い、ネットで検索して不安になられる方も多いのではないでしょうか。
今回は、「感覚」についてできるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
- 感覚過敏/感覚が鈍いと言われたけど、どういうこと?
- 感覚が大事と聞いたがよく分からないので教えてほしい。
- 感覚統合について知りたい。



“感覚”について知ると、子どもたちの言動が理解しやすくなりますよ^^
7つの感覚ってなあに?
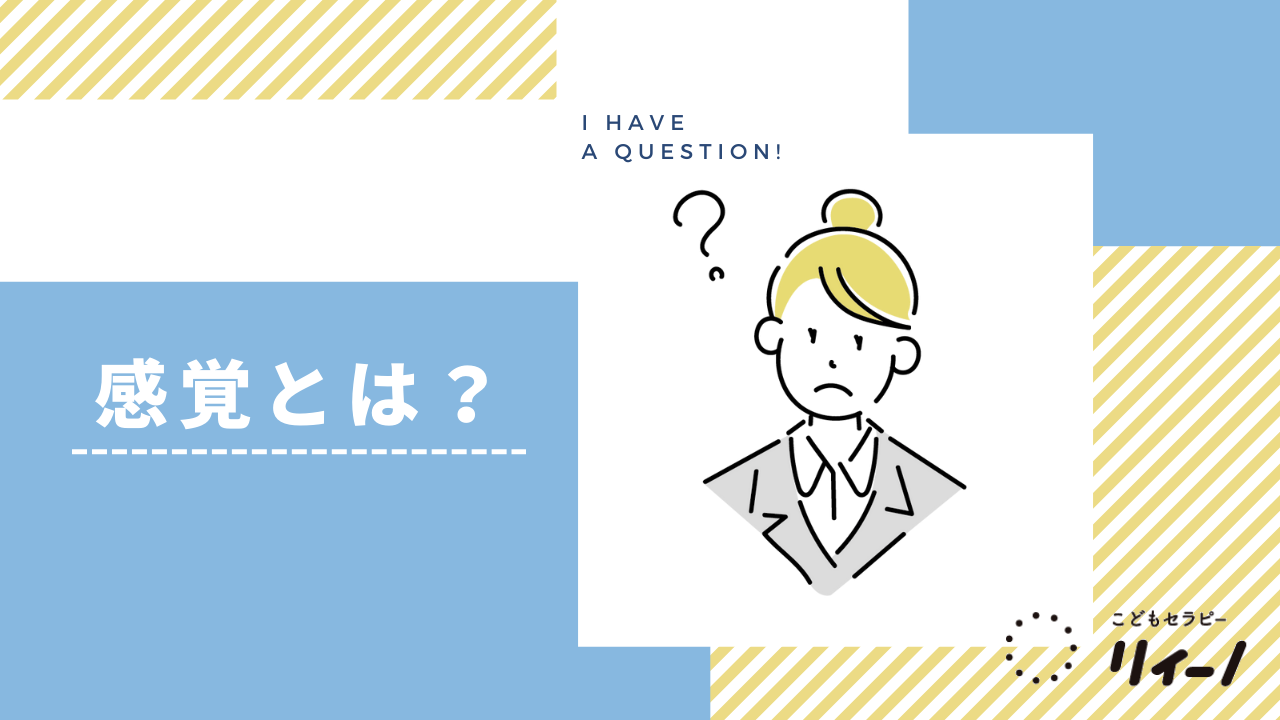
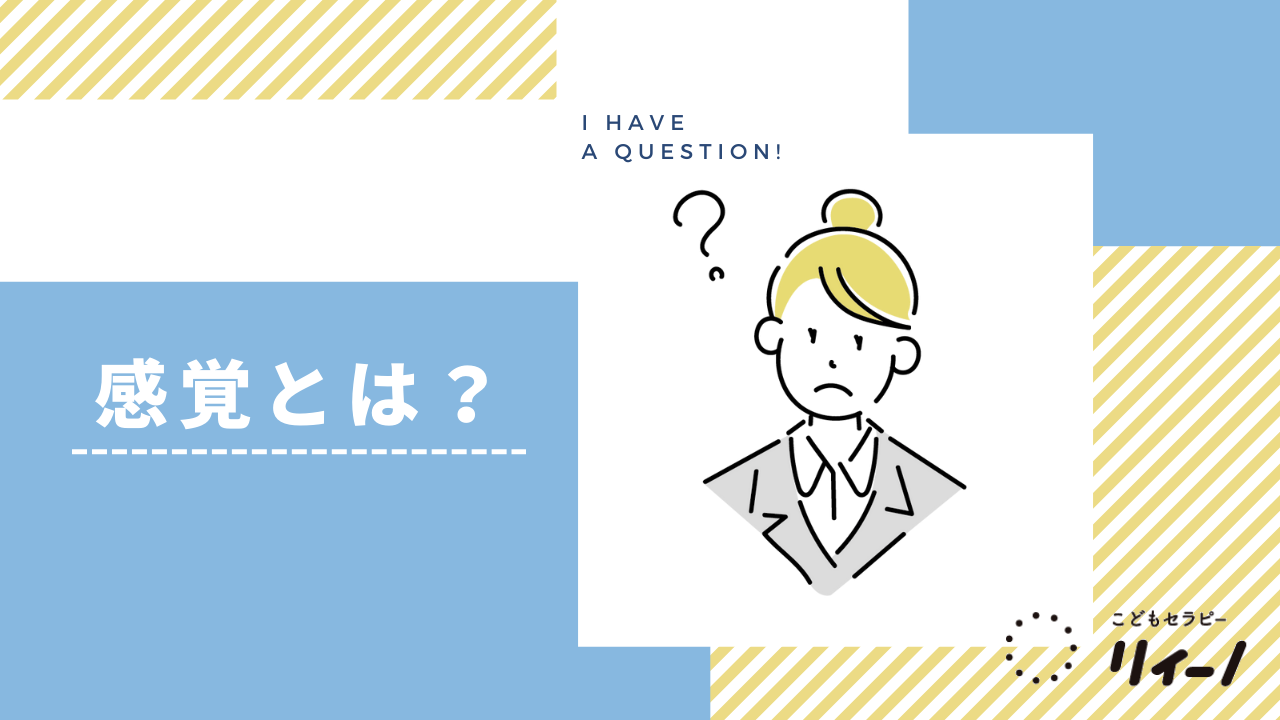
“感覚”の意味を辞書で調べてみると、下記のように書かれています。
① 目・耳・鼻・皮膚・舌などが身体の内外から受けた刺激を感じ取る働き。
また、感じ取った色・音・におい・温度など。
哲学的には、感覚は知覚の構成分であり、まだ意味づけられていないものとして知覚とは区別される。→ 五感
② (美醜・善悪など物事について)感じとること。
また、感じとる心の働き。感受性。感じ方。
Weblio辞書:三省堂 大辞林 第三版 「感覚」
ここで注目して欲しいところは、①の「身体の内外から受け取った刺激」



身体の「内側」と「外側」ってなに?



私も学び始めたころは、“外側”はイメージできるけど、
“内側”ってなに?と思っていたよ。
感覚には全部で7つあります。
この7つを身体の外側と内側の2つに分けて解説していきますね!
感覚には大きく分けて2つの種類がある
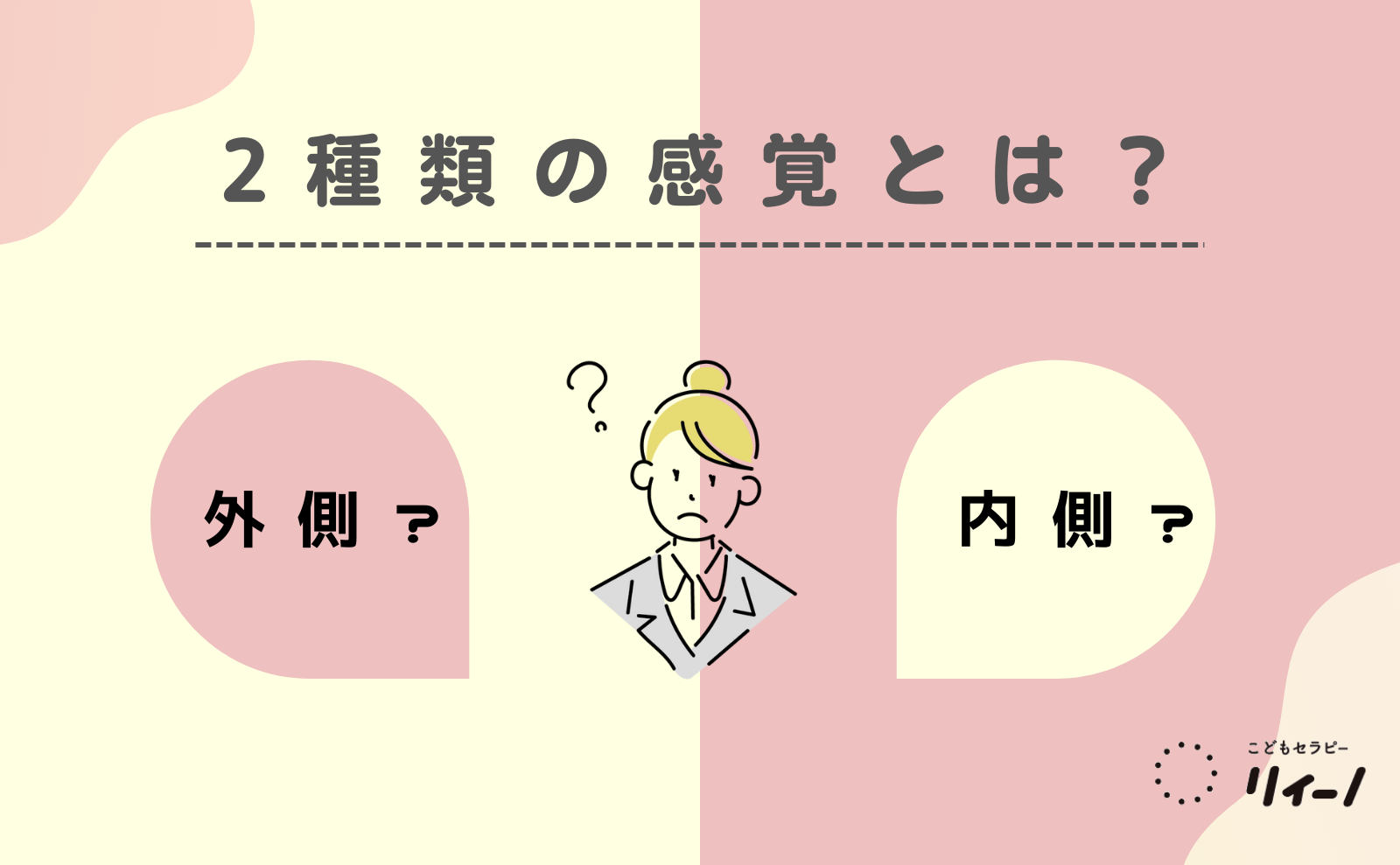
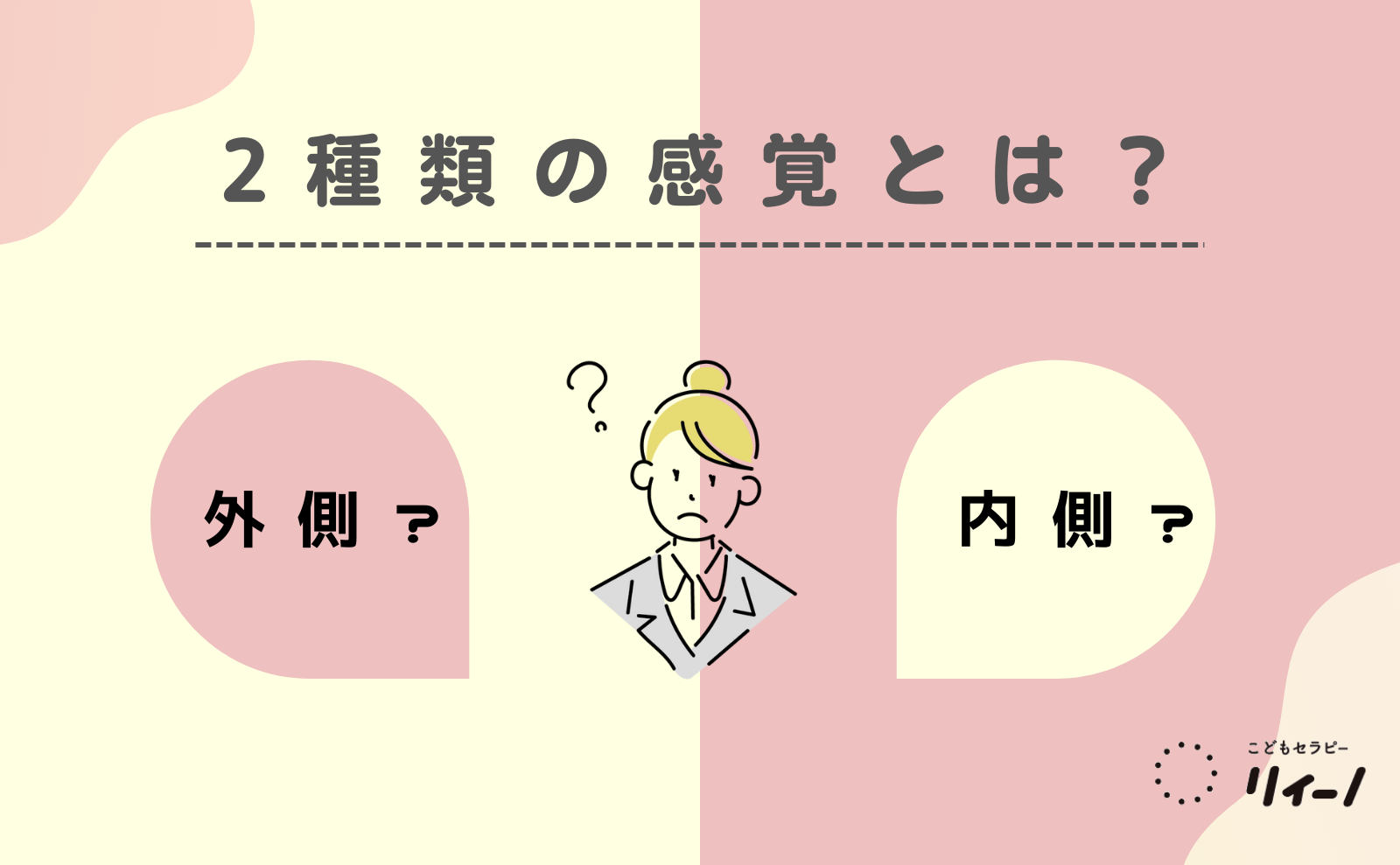
身体の外側からの感覚
外側からの感覚から入ってくる感覚のことで、一般的に、「五感」と言われるものです。
この感覚たちは、自分の周りの情報を教えてくれるはたらきをしています。
五感には、次の5つのものがあります。
- 視覚(見る):色、形、光
- 聴覚(聞く):音、声
- 嗅覚(嗅ぐ):におい、香り
- 触覚(触る・触られる):固さ/柔らかさ、素材の質感、温度
- 味覚(味わう):甘い、辛い、酸っぱい、塩っぱい、苦い
これらの5つの感覚は、上から順番に「目」「耳」「鼻」「皮膚」「舌」に感じるセンサーが付いています。
センサーが刺激を感じて反応すると、その情報が脳に送られていきます。



情報・・脳・・ややこしいなあ。



1つ例を挙げて説明しますね。
たとえば、目の前に「りんご」があったとします。
私たちは、どのように“りんご”を“りんご”と認識しているのでしょうか?


- 視覚(見る):赤い、丸い
- 聴覚(聞く):「りんご」という言葉の音
- 嗅覚(嗅ぐ):甘い香り
- 触覚(触る):ざらっとふわっとした感じ、丸い形
- 味覚(味わう):甘い、酸っぱい
これらの5つの感覚の情報が、私たちの脳に瞬時に伝えられ、「りんご」とはどんなものなのかを知ることができるんです。
このように、身体の外側からの情報を私たちは常に得て、周りの状況を把握したり、確認したりしているのです。
つまり、「五感は周りのものを知るための感覚」ということができますね。
身体の内側からの感覚
ここからは、身体の内側からの感覚について、お伝えしていきます。
この感覚をさらに2つの種類に分けて説明していきます。
自分の身体を知るための感覚
自分の身体を知るための感覚には3つあります。
1つずつ解説していきますね。



自分の身体を知る…?なんだそれ?



私も作業療法士になりたてころは、どういうこと?と思ってました。
また、ひとつ例を挙げて説明していきますね。



目をつぶったまま、胸の前で両手でバツ印をつくってください!
できましたか?


きっと、できたと思います。
“胸の前で両手をクロスにしたはずが、顔の前になっていた!”という方は、ほとんどいないはずです。
なぜ、目で見ていないのに、思った通りに胸の前でバツ印を作れたのでしょうか?



改めて考えてみると、不思議じゃないですか?



確かに。見て確認していないのに、できたよ。
どうして?
これは、身体が動いていることを教えてくれるセンサーが働いて、教えてくれているんです。



今、胸のところに両手が来てるよー。
両手がクロスになってるよー。
このように、身体が今どんなふうに動いているか、どこにあるかを脳に情報を伝えてくれます。
この感覚のことを固有受容覚※1といいます。
この感覚のおかげで、私たちは思い通りに身体を動かしたり、適度な力加減で物を操作したりすることができているんです。
固有受容覚のはたらきについては、自分の身体を知るための感覚。固有受容覚ってなあに?で解説しています。
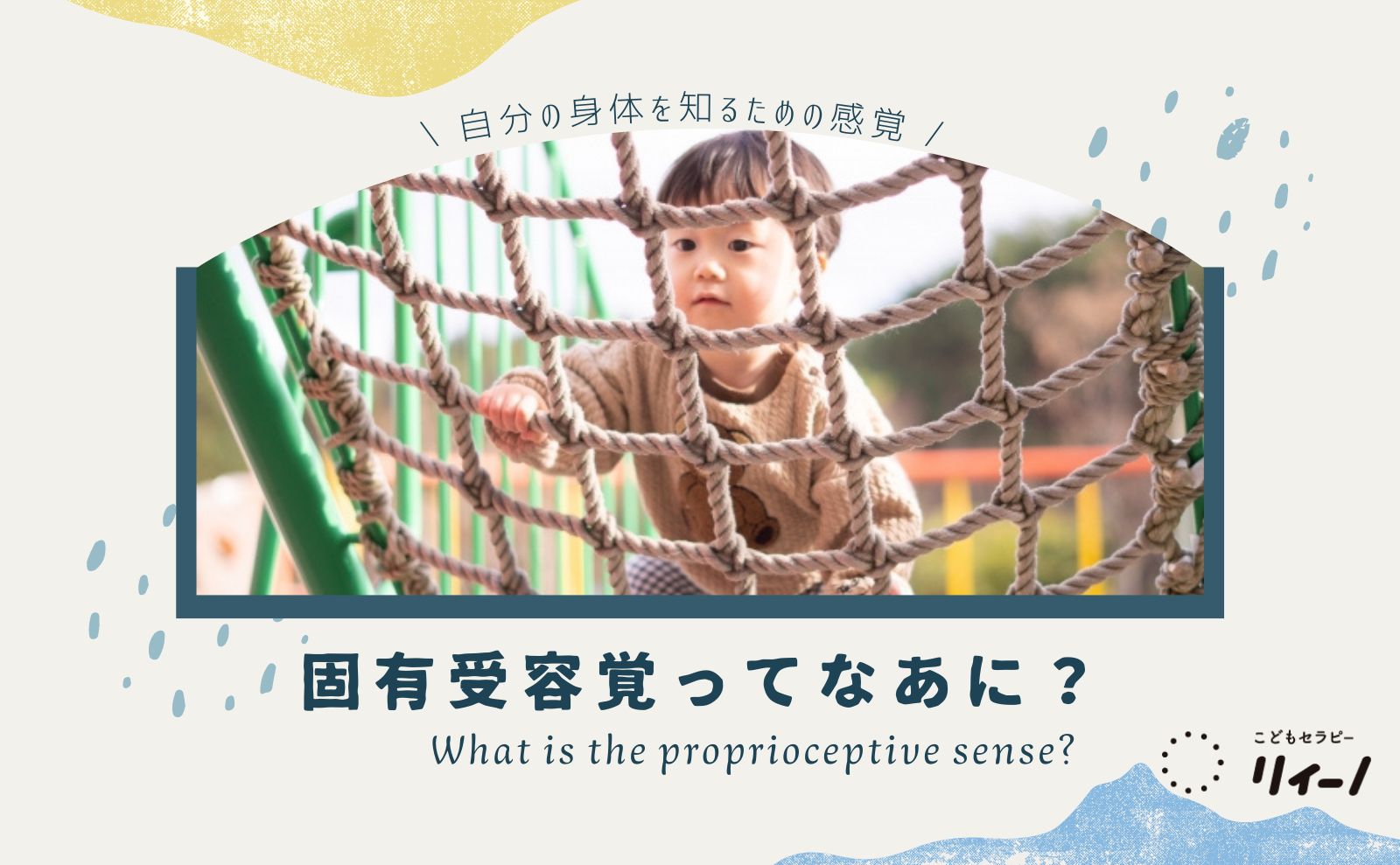
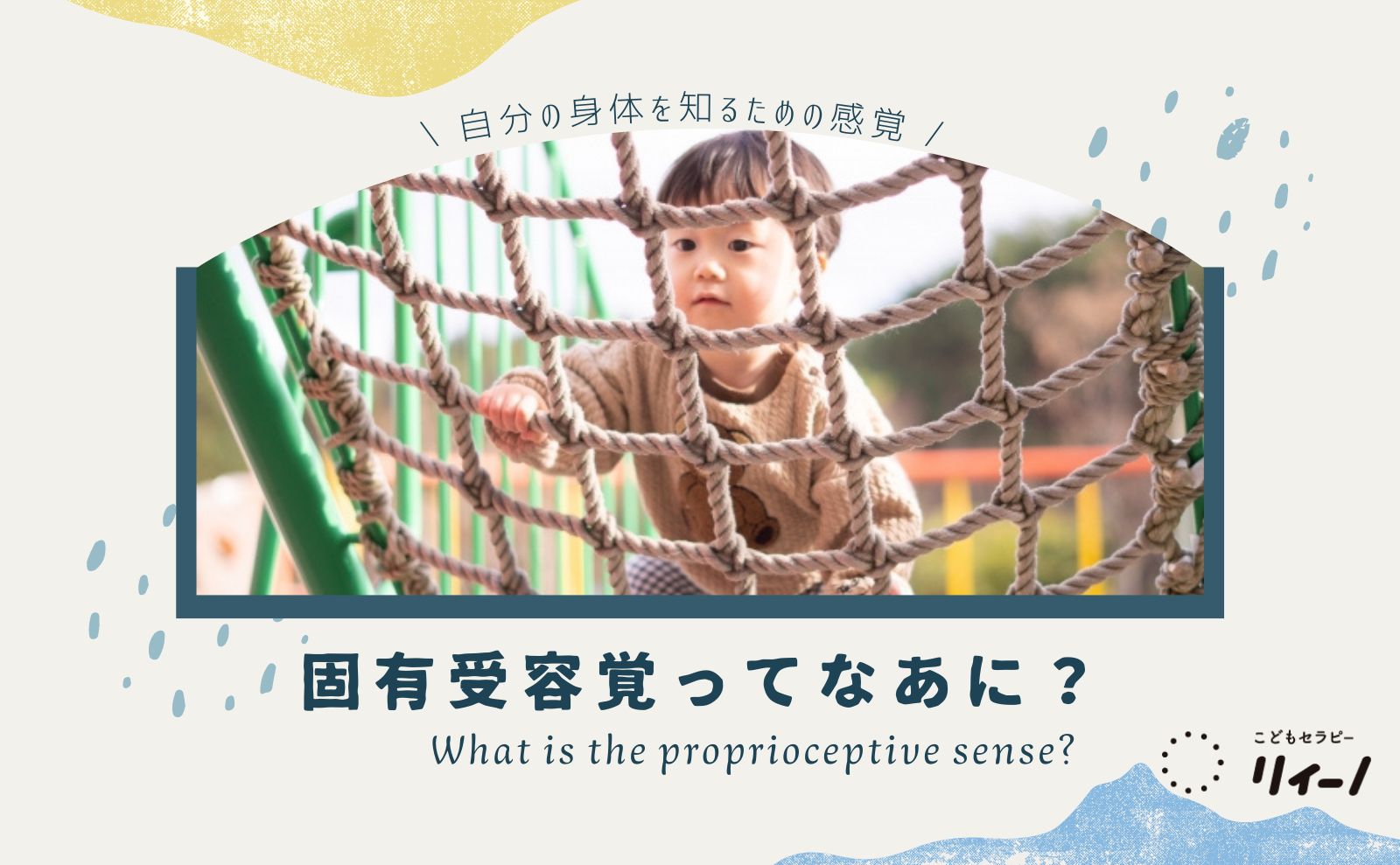



さっき、胸の前で両手をクロスをしたとき、
目を閉じていたけど、バランス崩してこけたりなかったですか?



こけてないよー。まっすぐ立ちながらできたよ。
実は、身体が傾いているかどうか、バランスが保てているかどうかを教えてくれるセンサーがあるんです。
この感覚のことを前庭覚といいます。
よく、“三半規管が強いね”と日常会話でも使うことがあると思います。
前庭覚とは、三半規管のことだと思っていただくとイメージしやすいかと思います。※2
前庭覚のはたらきについては、自分の身体を知るための感覚。前庭覚ってなあに?で解説しています。





これが最後の質問です。
両手を合わせてみてください。
自分の手の感触を感じれますか?



うん、感じれるよ。
手があたたかいよー。
このように、触ったこと・触られたことを教えてくれるセンサーが皮膚に付いています。
この感覚のことを触覚といいます。



ねえ、触覚って五感の仲間じゃなかったの?



よく気づきました!
触覚は、周りのことを知るためにも働くし、自分の身体の状態を教えてくれる働きもあるんです。
触覚のはたらきについては、自分の身体を知るための感覚。触覚ってなあに?で解説しています。


このように、身体の内側からの情報を私たちは常に得て、自分の身体がどんな状況にあるのかを意識せずとも理解できるようになっているのです。
つまり、「固有受容覚、前庭覚、触覚の3つの感覚は、自分の身体を知るための感覚」ということができますね。
内臓の感覚
内臓からの感覚とは、
おなかすいたー!
なんかしんどい!
トイレー!
という、身体の臓器から脳に伝えられる感覚のこと。
身体の調子や気分に大きく関わってくるものです。
ここまでの内容をまとめてみます。
- 身体の外側からの感覚:周りのものを知るための感覚
→五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)のこと。 - 身体の内側からの感覚:自分の身体を知るための感覚
→固有受容覚、前庭覚、触覚
→内臓の感覚
感覚が感じやすい、感じにくいって?
感覚の感じ方は、大人も子どももみんな異なります。
同じように感じている人って実はいないんです。
そして、感じ方は、時間帯やその日の体調、環境によって変化するものなのです。



それでは、例を2つあげて、説明しますね!
感覚の感じ方の違いについては、感覚の感じ方はみんな違う!?の記事で説明しています。


周りのことを知るための感覚(五感)が感じにくい、感じやすいとは?
実は、私たちも生活の中で、感覚が感じやすい日、感じにくい日があります。
過敏や感覚が鈍いと指摘されると不安が募りますが、誰にでも起こりうることなんです。
では、周りのことを知るための感覚が感じにくい、感じやすいとは、どういうことでしょうか。



風邪をひいたときのことをイメージしてみてください。
味や匂いなどの五感の感じ方は、いつもと何か変わりないですか?





鼻が詰まってごはんの匂いが分からないときがあるなあ。
他にも、こんな経験ないですか?
- たくさんの情報が目から入ると疲れてくる。
- 耳がキーンとする。
- ちょっとした音にイライラする。
- 食べものの味が、よく分からない。
これが、周りのことを知るための感覚(五感)をうまくキャッチでてきていない状況です。
うまく感覚の情報が得られないと、普段と比べると少し生活がしにくくなりますよね。
そして、このような感じ方のことを「過敏」や「鈍麻(鈍い)」と表現することがあるんです。
誰しもが、生活の中で感覚の感じ方が過敏になったり、鈍くなったりすることがあるということを知ってもらえたらと思います。
自分の身体を知るための感覚(固有受容覚、前庭覚、触覚)が感じにくい、感じやすいとは?
例えば、触るのが苦手だと“触覚過敏”と言われたり、音が苦手だと“聴覚過敏”と言われたりしますよね。
最近では、子どもの業界でよく耳にする言葉の1つかもしれません。
これについて調べ出すと、不安を煽るような内容もたくさん出てきますよね。
そもそも、身体の内側の感覚が感じやすい、感じにくいとは、どういうことなのでしょうか。





下の写真のように、手袋をつけてスマホを操作することをイメージしてください。
素手で操作するときと、使いやすさはいかがでしょうか。



思うように操作ができないよ…
スマホの反応もいまいちだね。
なかなか操作がしにくいことは想像できますよね。
その原因の1つとして、触覚からの情報が十分に得られいことや、固有受容覚から指がどう動いているのかを感じにくいことが挙げられます。
子どもたちの中には、手袋をはめているかのように感じにくいタイプの子、反対にいつもビリビリとしびれているような感じやすいタイプの子がいます。
このように日頃から感じているとすれば、細かなものの操作がやりづらくて億劫だったり、いろんなものを触るのが嫌になったり、ということが想像しやすいですよね。
つまり、私たちは、7つの感覚がしっかりと働いてくれているからこそ、思いのままに身体を動かし、新しいことを学び、仲間とやりたいことができるという、支障のない日々を送ることができるのです。
もし、この感覚がうまく働かないと、さまざまな場面でやりにくさが出てきてしまいます。
どの感覚が受け入れやすく、苦手なのかを知ってあげることで対策を練ることができます。
それぞれの感覚については、下記のブログをお読みください。
どうして感覚が大切なの?
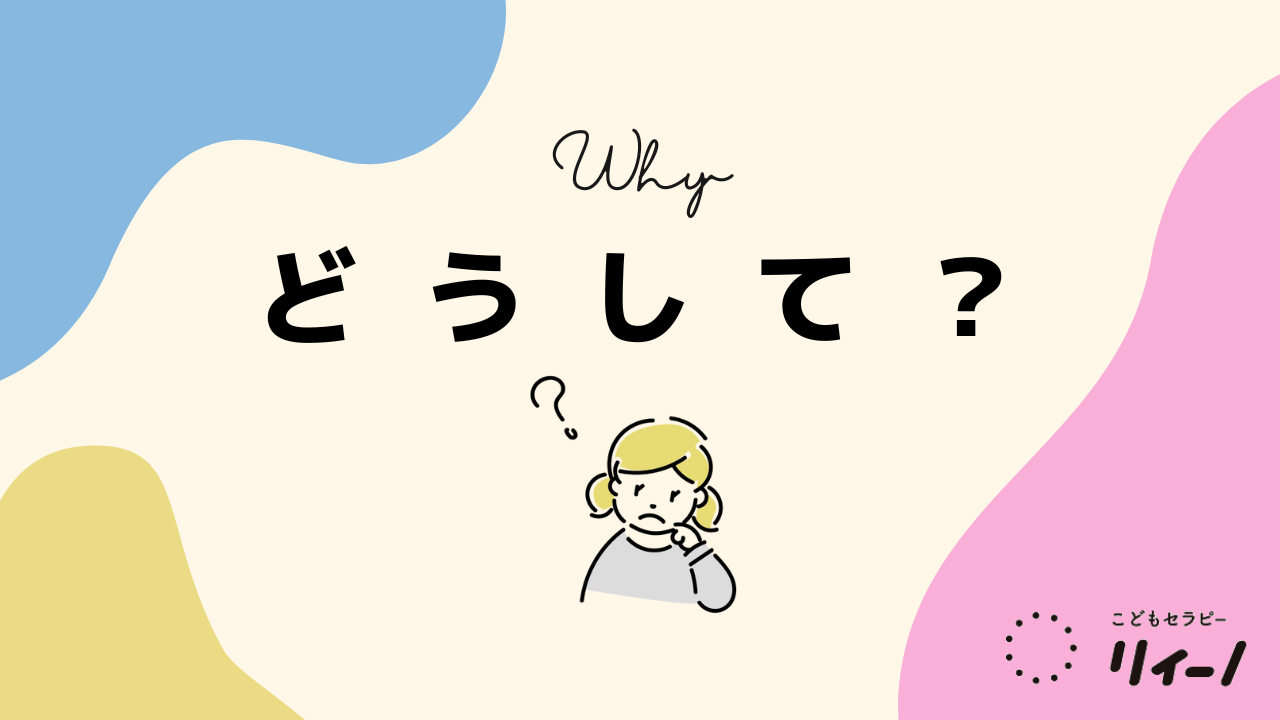
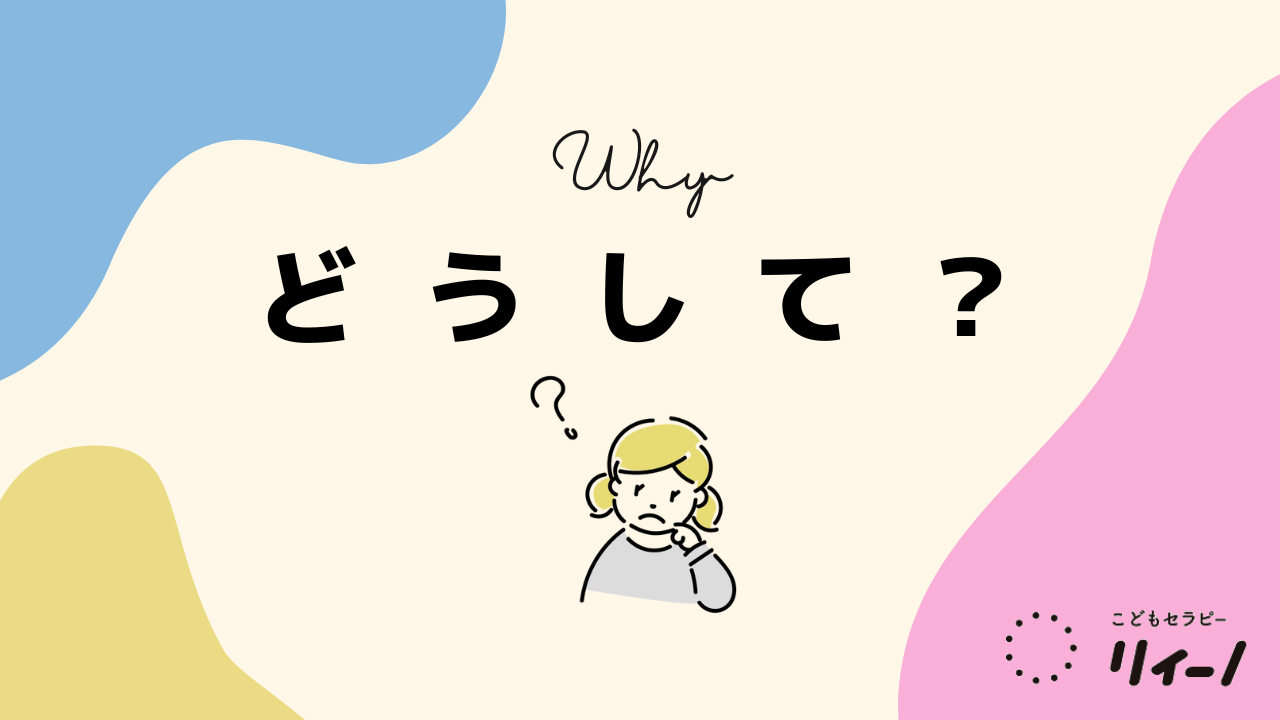
さきほどの2つの例を通して、感覚の感じ方がいつもと違うと、生活に支障が出ることを知っていただけたかなと思います。
これらの7つの感覚は、お母さんのお腹の中にいるころから育ち始めるものがほとんどです。
生まれてからは、だっこされたり、いろんなものを触ったり、食べたり、遊んだり…と、全身で感覚を味わい始めます。



下の感覚統合のピラミッドの図を見てください。
感覚が一番下に書かれていますよね(※味覚と嗅覚は省略しています)。


感覚は、脳の栄養素と言われるほどとても重要なものです。
子どもたちが育っていく上で、感覚は全ての基盤となります。
「いっぱいいろんなことを経験しよう!」と言われる理由は、ここにあるのです。
おすすめの本


感覚統合Q&A 改訂第2版 ー子どもの理解と援助のために
いつもリィーノの保護者の皆さんや保育士・教師の皆さんにことあるごとに紹介している本です。
感覚についてとても分かりやすく書かれています。
また、よくある困りごとがたくさん載っていて、なぜそれが起こるのかを感覚の視点から説明がされています。
お子さんの対応を考えるヒントになると思います。
まとめ


感覚の感じ方は、大人も子どももひとりひとり異なります。
「感覚」について正しく知識を付けておくと、子どもたちの不思議な言動の理解や対応に繋がっていきますよ^^
それでは、今回の内容のまとめです。
- 感覚とは、身体の外側と内側から受け取った刺激のこと。
- 身体の外側の感覚とは、五感のこと。
- 五感とは、周りのことを知るための感覚。(見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わう)
- 身体の内側の感覚には、自分の身体を知るための感覚と内臓の感覚がある。
- 自分の身体を知るための感覚には、固有受容覚・前庭覚・触覚がある。
- 感覚が過敏になったり、鈍くなったりは誰にでも起こること。
- 感覚は子どもたちが発達していく上で全ての基盤となるとても重要なもの。
- 感覚は、普段の生活や遊びの中で養われていく。
なかには、生活にものすごく支障が出るほどに感覚の感じ方がアンバランスになっているお子さんがいらっしゃいます。
その場合は、1人で抱え込まずにいつでもご相談くださいね。
一緒に原因と対策を考えていきましょう!